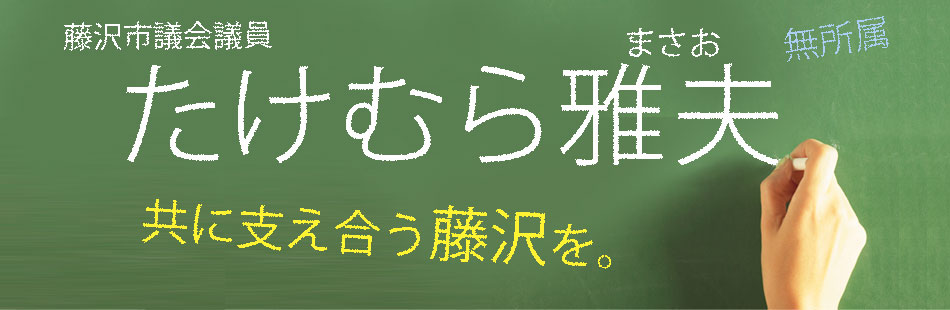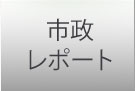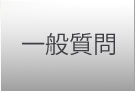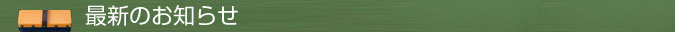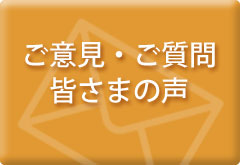2011年に改正された「障害者基本法」の第1条には、こんな言葉が書かれています。
「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される…」
「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」
この「障害の有無」を、「男女の性別や性指向」「国籍や民族」「大人や子ども」などと置き換えてみてください。
すべてに通じる、たいせつな理念だと思います。
「共に生きる社会」
これからの教育は、そんな教育をめざしたい。
これからの藤沢も、そんなまちをめざしたい。
そのために、私もみなさんと一緒に考え・話し合い・とりくみます。
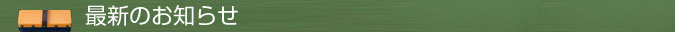
2024年6月14日
|
市政レポート「藤沢での実態調査から8年、『ヤングケアラー支援法』が成立」を掲載しました。
2016年に藤沢の教員を対象に実施された「ヤングケアラー実態調査」から8年、ようやく「ヤングケアラー支援法」が成立しました。
この法律の内容と意義、実態調査以降ヤングケアラーにかかわる認識はどのように深まってきたのかについて、まとめました。
|
2024年1月20日
|
市政レポート「忙しすぎる子ども、忙しすぎる先生」を掲載しました。
いま、「不登校」の子どもたちが激増しています。そして、不登校の子どもたちと軌を一にして心を病んで退職する先生も増加の一途です。
そのターニングポイントは2012年。「ゆとり教育」が否定されて、学習内容を大幅に増加させた新指導要領が本格実施された年です。
学校の教育内容が過度に多すぎてキャパシティを越えている状態を「カリキュラム・オーバーロード」と言います。今や日本の学校はまさにカリキュラム・オーバーロードの状態になってしまっているのではないでしょうか。
その状況と、改善への途を探りました。
|
2024年1月9日
|
市政レポート「『ヤング』だけでは終わらない。 労働問題としての『若者ケアラー』」を掲載しました。
いまようやく「ヤングケアラー」の存在が広く知られるようになってきました。ですが、その介護やケアは18歳を過ぎれば終わるわけではありません。大学生や社会人になっても介護やケアが続くこともあります。18歳を過ぎてから介護が始まる場合もあるでしょう。
介護やケアを担っている18歳からおおむね30歳代の若者は「若者ケアラー」と呼ばれます。ケアの内容は子どもと同じですが、そのケア責任はより重くなることもあります。
「若者ケアラー」にはどのような支援が必要なのでしょうか。とりわけ「労働問題」としての視点から考えてみました。
|
2023年11月3日
|
市政レポート「日本の性教育はなせ停滞したのか 性教育バッシングと包括的性教育」を掲載しました。
2000年代に吹き荒れた「性教育バッシング」によって、日本の性教育は長い「冬の時代」を過ごしてきました。
しかし性教育とは単に体の造りを学ぶ教育ではありません。性について学ぶことは「自分を大切にする」だけでなく「相手を大切にする」ことを学ぶ、大切な「人権」の教育なのです。
いまユネスコが提唱している「包括的性教育」とは何か、これからの性教育に求められるものは何か。この間の歴史とこれからの方向性についてまとめました。
|
2023年5月3日
|
市政レポート「私たちのとなりにいる『難民』」を掲載しました。
日本が「難民鎖国」と呼ばれるほど、難民の受け入れに対してきわめて否定的な国だということをご存じでしょうか。
2021年に日本が受け入れた難民の人数は74人、これは難民申請者の0.77%に過ぎません。諸外国を見てみると英国63%、カナダ62%、米国32%、ドイツ25%です。国連の難民高等弁務官からも懸念が表明されているのが日本の難民政策なのです。
しかも申請不認定者に対する劣悪な入管施設への収用や強制国外退去、そして、これをさらに後退させるような入管法の改悪‥‥何が問題なのかを整理しました。
|
2023年4月27日
|
市政レポート「『ゆとり教育』再考-『ゆとり教育』で本当に学力は低下したのか?-」を掲載しました。
今から15年ほど前、子どもたちの「学力低下」が大きな問題となりました。そのきっかけは2006年、国際学力比較調査(PISA)で日本の高校1年生の点数や順位が前回と比べて低下したことでした。その原因として猛烈なバッシングにさらされたのが、2002年から導入されたいわゆる「ゆとり教育」でした。
ですが2006年に「学力低下」が喧伝された高校生たちは、学齢期の多くを「ゆとり教育」以前の指導要領で学んでいたのです。冷静に考えれば当たり前のことですが、「ゆとり教育」が始まって間もない2006年の時点でその影響が計れるはずがありません。
「ゆとり教育」による授業時間削減の影響をいちばん受けたのは2012年の調査に参加した世代です。この2012年調査の結果を見なければ「ゆとり教育」の結果は判断できません。
では、その結果はどうだったのでしょう。「事実」をもとに、冷静に検証しました。
|
2022年7月20日
|
市政レポート「教員免許更新制とは何だったのか」を掲載しました。
「教員不足」の一因となり、学校現場に多大な負担と混乱をもたらした教員免許更新制。
その発端は現場からの要望ではなく、第1次安倍内閣が設置した「教育再生会議」の報告です。安倍政権の「負の遺産」だったのです。
その成立から廃止までの経過と今後の課題についてまとめました。
|

藤沢市議会議員
竹村雅夫(たけむらまさお)
- ●子ども文教常任委員会(副委員長)
- ●補正予算常任委員会
- ●議会運営委員会(委員長)
- ●行政改革等特別委員会